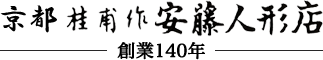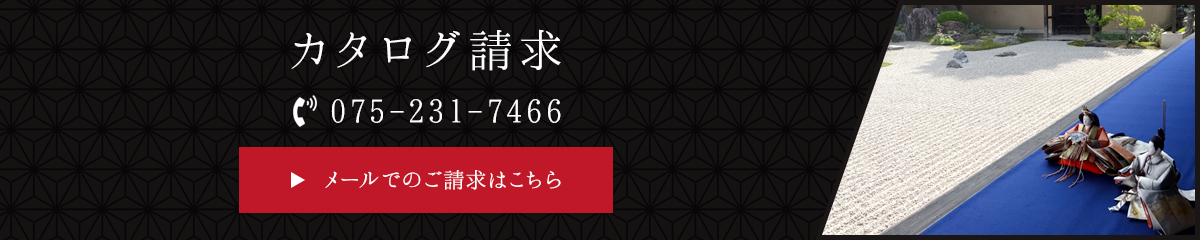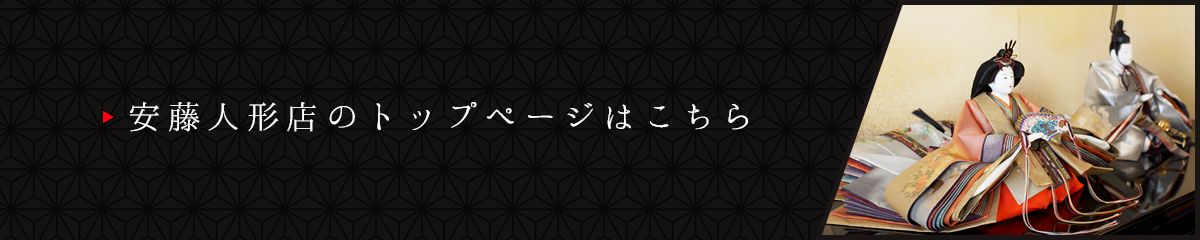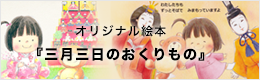五月人形の読み方とは?間違えやすい読み方
男の子の健やかな成長を願って飾る「五月人形」。端午の節句には欠かせない伝統的な飾りですが、その読み方を間違えて覚えている人も少なくありません。特に「さつきにんぎょう」と読んでしまう方も多いのですが、実はこれは誤りです。
本記事では、五月人形の正しい読み方と間違えやすい読み方の違いを解説し、なぜ「五月人形」と呼ばれるのか、その由来や意味についても詳しくご紹介します。そして、最後には京都での五月人形選びについても触れ、伝統と格式を兼ね備えた逸品を探す際の参考になる情報をお届けします。五月人形の正しい読み方
「五月人形」は「ごがつにんぎょう」と読みます。 この読み方は日本の伝統文化に根ざしており、「五月(ごがつ)」は端午の節句が行われる5月を指し、「人形(にんぎょう)」は武士の鎧兜や武将の姿を模した飾り物のことを指します。そのため、「ごがつにんぎょう」と読むのが正しく、古くから伝わる正式な呼び名となっています。間違えやすい読み方 さつきにんぎょう
多くの方が間違えてしまうのが「さつきにんぎょう」という読み方です。 「五月(さつき)」は、和風月名(わふうげつめい)として5月を表す言葉です。そのため、「さつきにんぎょう」と読んでも意味は通じそうに思えますが、実際には一般的ではありません。 また、「さつき」という言葉は五月の別称として使われますが、伝統的な節句飾りである「五月人形」に対しては「ごがつにんぎょう」という正式な読み方が用いられます。このため、「さつきにんぎょう」と読んでしまうと、文化的に違和感が生じることもあります。五月人形と呼ばれる理由
では、なぜ「五月人形」という名称が用いられるのでしょうか。1. 端午の節句と関係が深い
「五月人形」は、端午の節句(5月5日)に飾る人形の総称です。端午の節句は、古くから男の子の健やかな成長と健康を願う行事として行われてきました。そのため、この節句に飾る人形を「五月人形」と呼ぶようになったのです。2. 武士の文化が影響
日本の武家社会では、男の子の誕生を祝う際に、鎧兜を飾る風習がありました。これは、子どもを守る象徴として武士の甲冑が尊ばれたためです。この風習が庶民にも広まり、武将の姿を模した人形が作られるようになり、次第に「五月人形」として定着していきました。3. 「五月(ごがつ)」という言葉の普及
端午の節句は中国から伝わった風習ですが、日本独自の文化として発展し、5月に行われる行事として広く知られるようになりました。そのため、正式な呼び名として「五月人形(ごがつにんぎょう)」が定着したのです。まとめ
「五月人形」の正しい読み方は「ごがつにんぎょう」であり、「さつきにんぎょう」は誤りです。端午の節句に飾る人形としての歴史的背景や武士文化との関係を考えると、正式な名称が「ごがつにんぎょう」となるのは自然なことです。 そして、伝統的な五月人形を選ぶなら、歴史ある京都がおすすめです。京都には、長い歴史を持つ人形店が多く、職人の技が光る逸品が揃っています。素材や仕立てにこだわりたい方にとって、京都の五月人形はまさに理想的な選択肢となるでしょう。お子様やお孫様の健やかな成長を願い、ぜひ京都で伝統の五月人形を選んでみてはいかがでしょうか。上記に掲載しております基礎知識・用語以外にも、五月人形について
不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
電話番号 075-231-7466
お気軽にお問い合わせください。