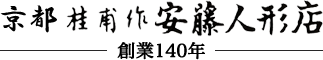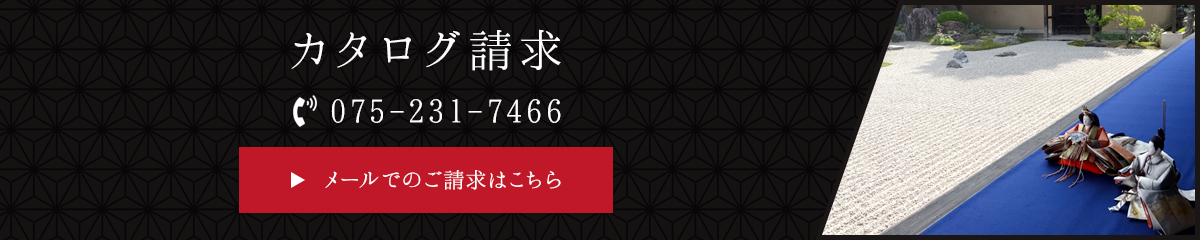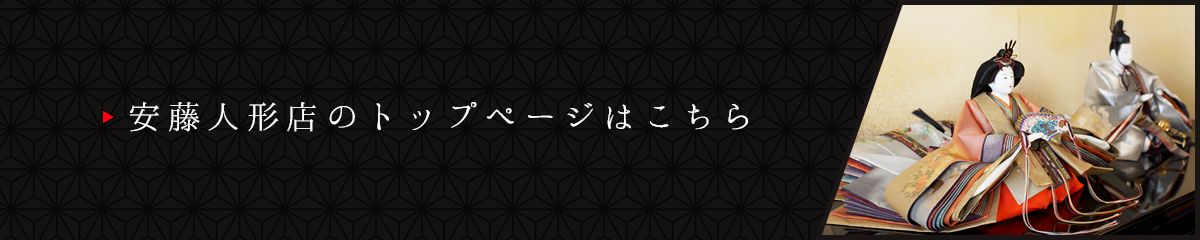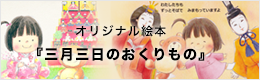五月人形の飾り方などにまつわるしきたり
五月人形は、端午の節句に飾ることで、男の子の健やかな成長と無病息災を願う大切な風習です。特に日本では、長い歴史の中でさまざまなしきたりや決まりが受け継がれてきました。初めて五月人形を飾るご家庭や、お孫さんの誕生を機に五月人形を用意しようと考えている方にとっては、どのように飾ればよいのか、いつまでに準備すればよいのかなど、疑問に思うことも多いでしょう。
この記事では、五月人形を飾るしきたりや「一夜飾り」について詳しく解説し、さらに京都で購入するメリットについてもご紹介します。ぜひ参考にして、伝統を大切にしながら、ご家族の新たな節目を素敵なものにしてください。五月人形を飾るしきたりとは?
五月人形の意味と歴史
五月人形は、鎧や兜、武将の人形など、勇ましい姿をした飾りを通して、男の子の健やかな成長を願うものです。その起源は平安時代にさかのぼり、貴族の子どもたちの厄除けとして「菖蒲(しょうぶ)」を飾る風習がありました。これが武士の時代に入ると、「尚武(しょうぶ)=武を尊ぶ」に通じることから、鎧や兜を飾る習慣へと変化していきました。 現在では、鎧兜や武者人形だけでなく、金太郎や桃太郎をモチーフにした可愛らしい五月人形もあり、家庭ごとの好みや飾るスペースに合わせて選ぶことができます。いつ飾るのが正しい?
五月人形は一般的に、3月下旬から4月中旬にかけて飾るのが良いとされています。遅くとも4月中には飾るのが望ましく、余裕をもって準備することが大切です。誰が用意する?
五月人形は、昔から母方の実家が贈るものとされてきました。しかし、現在では必ずしもこの慣習に従う必要はなく、両親や父方の実家が用意する場合もあります。家庭ごとに話し合い、無理のない形で準備するのがよいでしょう。一夜飾りとは?
一夜飾りを避ける理由
「一夜飾り」とは、五月人形を端午の節句の前日に急いで飾ることを指します。これは縁起が悪いとされ、避けるべきしきたりの一つです。その理由として、以下のような考え方があります。- 神様に対する失礼 短時間で形だけ整えるのは、神様に対して誠意がないと考えられています。
- 葬儀の準備を連想させる 一夜で準備を整えることは、急ごしらえの葬儀を思わせるため、不吉とされています。
- 準備不足によるトラブル回避 直前の準備では、飾る場所や人形の状態をしっかり確認できず、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
いつまでに準備すればよい?
端午の節句(5月5日)の1週間前までに飾るのが理想的です。余裕をもって準備することで、家族みんなで楽しみながら飾ることができます。また、飾り終えた後は、できるだけ早めに片付けることも大切です。長く出しっぱなしにすると、厄を家に留めることになってしまうため、5月中旬頃には収納するのがよいでしょう。まとめ
五月人形を飾るしきたりには、古くからの意味や伝統が込められています。適切な時期に飾り、一夜飾りを避けることで、より良い形で男の子の成長を願うことができます。 また、五月人形を選ぶ際には、伝統的な技術が息づく京都の職人によるものがおすすめです。京都の人形店では、細部までこだわった美しい五月人形が揃っており、一生ものとして大切にできる逸品が見つかるでしょう。お子さまやお孫さまのために、ぜひ京都で特別な五月人形を選んでみてはいかがでしょうか。上記に掲載しております基礎知識・用語以外にも、五月人形について
不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
電話番号 075-231-7466
お気軽にお問い合わせください。